来栖瓏=演出家。
室生艸人=老劇作家。
室生蓮司=艸人の長男、陶芸作家。
筥子=蓮司の妻。
尚彦=艸人の二男、役者。来栖に主役に抜擢される。
一人=艸人の三男。ヴァイオリニスト。 室生公成=艸人の弟。数奇者として京都に在住。
室生正円=公成の一人息子。音楽家。来栖と一緒に仕事をしている。
蕁草の園(5)
中村祐之
イラスト・山口喜造
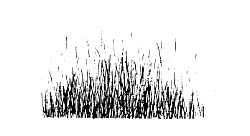
エククスの頭首(くび)
「見てごらん。」
来栖はバルコニーの上から浴場の青年たちを指さした。
浴場といってもそこは一種のトレーニングルームを兼ねているジムであった。ただ一面大理石で磨かれていることが一人には不思議に思われた。
床の小さな穴から水蒸気が吹きだして青年たちの裸身を隠している。
彼らはそれぞれかってに自由な運勤をしながら躯を鍛えている。
汗がふきだして胸が朱に染った青年がサウナから飛び出すと思いきってプールの中に身をおどらせた。
歓声が起った。
浴場の丁度まん中で一組の青年がレスリングをしている。互いに力が互角らしくなかなか技がきまらない。
まるで二匹の牡鹿が角を競いあっているような光景である。
一人は青年の小麦色に輝いたたくましい肌に思わず見とれた。均整のとれた肉体が飛びはねている姿はそのまま舞踏のように白い軌跡を描いては消えていく。
美しい、一人はしばらく彼らに見蕩れてしまった。
「あの人たちは護れなのですか。」
一人は自分の白い肌を思い浮べて困惑しながら訊ねた。
「みんな俺の弟子たちだ。役者もいれば舞踏家もいる。素晴しいとは思わないかね。ここでこうして躯を鍛えさせて、自分を芸術にする。肉体がこんなにも美しくなることを誰れが想像したろう。」
来栖はうっとりとした目で青年を眺めた。彼らはまったく伸び伸びと自分の肉体を磨き上げることに耽溺していた。
まるで彫刻のようだ。
一人は野外庭園に迷い込んだ時の事を思い出した。道の並木に平行して幾体もの彫像がならべられていた。彼はその下をくぐりぬけながら本当にこれが人間の躯なのだろうか、といぶかしんだ。
だが、目の前の男たちの躯はまさしくその悪魔を払いのけるのに十分に完壁だった。
まさしく神が作り上げた傑作が目の前にあるのだ。
一人は嘆息をついた。
「青年の肉体は一つの芸術だよ。美しい神秘なんだ。それに比べれば女の躯など安物でつまらないものだ。」
一人は瓏の顔を見つめた。純粋な瞳の輝きが一瞬、残酷な光をおぴて獲物を傷つける刃を映した。
一人は寒気におそわれた。ここから逃げ出したかった。
が、そうするのができないのはやはり瓏の心の奥に何か一人がのぞきこめない情熱があるような気がするからであった
それが何んなのか、判らない。
この人には何かが隠されている。
運命の残忍さを一人は予感していた。自分ばかりでなく、まわりの愛情ある人たちもすべて切り裂いてしまうようなひどく辛い運命が待っている。
しかし、今の彼には瓏の心の邪悪な愛情に逆に引かれるのであった。
この人の仮面の奥にはどんな顔が隠されているのだろう。
一人はそれを知りたくてここに来たのを忘れてしまっていた。
「あれを見てごらん。」
物思いに沈んでいた一人に来栖が声かけた。
「あの青年を知っているだろう。」
部屋のまん中にいる美貌の青年を指差した。
蒸せた湯気ではっきりしなかったが先程の組み撃ちをしていた青年らしく、相手を倒した歓声に囲まれていた。
勝者の祝杯だろうか、銀色のリュトンを高く挙げた青年の顔が見えた。
一人は思わず息を呑んだ。
「兄さん!」
叫び声が壁にこだまして響きわたった。
浴場の青年たちが一斉にバルコニーを見上げた。青年の目が一人を捉えた。
「一人……」
青年は呆然と立ちすくんだ。
どうして弟がここに来ているんだ。それよりも自分の淫らな婆を見られたこに当惑した。
兄弟はしばらく無言のまま見つめあった。まわりの者は好奇の目で眺めていだが、来栖の視線だけは冷静に二人の若者そそがれていた。醒めて邪悪な光がその中に宿っている。
どうやって尚彦に声をかければよいのだろうか。一人はためらった。
彼を驚かせたのは尚彦の裸の胸に緑と青で刺青させたエクウスの頭首であった。
今にも飛び出さんばかりに目をむいたエクウスが熱気で灼けた肌にたて髪をなびかせている。
「兄さん、その刺青はどうしたの。」
一人はじっとそれを見つめた。線の刺し方からかなりの腕の職人の仕事であることは分かった。胸から腹にかけて一息に彩られた生々しさがまるで生物のように波うっている。
「そんな余計な事はどうでもいい。それよりも、お前はなぜここにいるんだ。」
一人は答えに詰った。自分でもここに居る理由が解からなかった。
まわりの青年たちの好奇の目が一人にそそがれた。彼だけが服を着けていることが、ひどく恥かしいように思われた。あから様に彼を見くだす者もいた。
ここはお前のような青白い小僧が来る所じゃないぞとさも言いたげな視線である。
あるいは瓏の新しい恋の相手だとでも思ったのだろうか、冷たい刺すような視線が痛いほど分かった。
「一人は俺が呼んだんだよ。」
来栖が重たい口を開いた。
一瞬、尚彦の顔が青ざめた。血の気が失せていまにも倒れそうであった。
この様な兄のあられもない姿を見るの一人はしのぴなかった。
確かに一人は来栖にあこがれていた。丁度青年が麗人にあこがれるような、ほのかな恋心に近い気持ちだった。
しかし、兄のような何もかも言うがままの恋ではなかった。
これではまるでハーレムではないか――。
なぜ兄はこんな事をしてまで来栖に従っていなければならないのだろう。
先程まであんなに美しく見えた青年たちの裸身がロボットのような金属的な味けないものに写った。
わけの分からない怒りが一人の裸にこみ上げて来た。
「どうしようもなく苦しくなって、彼を呼んだんだよ。]
「一人を呼んで何をしようというんですか。」
尚彦はヒステリッタに叫んだ。
「ヴァイオリンを聴きたかった。俺の心には一人のひく曲が必要なんだ。」
来栖はとぼけたように答えた。
「兄さん、その刺青は何?」
ようやく落着いた一人が訊ねた。
「悪戯だよ。冗談にやったのさ。ここにもう一つある。」
と言って尚彦は左手の甲を一人に示した。
真紅の薔薇が一輪描かれていた。
「尚彦に刺青をしたのはこの俺だ。]
「あなたが……。」
「そうだ。俺の命じたままに馬の刺青をしたんだ。」
「何んでそんなことをしたの。父さんに知れたら大変なことになるのに。」
「ハハハハ」
来栖は高らかに笑った。それにつれてどっと笑い声が起った。
「君はまるで少年のようだ。」
来栖は口唇をなめながら一人を見た。
「もっともその美しい瞳が俺を狂わせるのだが……。」
「一人、ここはお前の来る所ではない。早く帰れ。ここは役者の修業の場所なんだ。毎日が血の出るような開いの場所だ。
ここに入れてもらうことでさえ大変な
名誉なことなんだ。」
「役者の勉強だけじゃないがな。」
遠くで誰れかがからかった。またしても爆笑が起った。
「俺はここに居て、すごく自分の生きがいを感じている。躯のあらゆる所に力がみなぎつている。不思議に刺青をしてから自分の思うように躯が動くんだ。」
「ぼくにはそう思えない。兄さんは無理をしている。昔のようにぼくを正面から見れなくなっている。兄さんは間違っているよ。」
一人は鋭い声で兄に言った。
今まで浴場に漂っていた熱気がいつの間にか引いて底寒くなった。
尚彦の顔が怒りでみるみる紅潮した。興奮して今にも一人に殴りかかろうとした。
来栖は相かわらず冷静に二人を見つめていた。
まるで兄弟の争いを予見したかのように、巧みに操っているような目つきであった。
尚彦の一撃が一人の頬をまさに打たんとした。
その瞬間、尚彦の手は空中で静止した。荒々しい挙がしっかりと後ろから掴まれた。
来栖は尚彦の手を突き放した。その反動でよろめいた彼の右手には赤く痣ができて腫れあがっていた。
「弟の手をあげるとは感心しないね。見ろ、お前のとんでもない余興で風呂が冷えてしまった。お前の躯を見ろ。まるで羽をむしられた鳥のようだ。」
尚彦は首を垂れたまま黙った。
「一人君、ぴっくりさせてすまなかった。最初から君に話しておけば良かったが、尚彦は俺があづかっている。役者にする為には少し荒修業もしなくてはならない。
ここにいる時は誰れの干渉もうけない。
例え君であってもだ。」
一人は来栖の凛とした声に次第に冷静さをとりもどした。
「それよりも、君にこれを使って演奏してほしいんだ。」
彼は一人の前に一丁の黒ニスで塗られたヴァイオリンを置いた。
「このヴァイオリンを君に引いてもらうのを俺は夢にまで見ていた。何度も同じ夢を見て苦しんだ。さあ、お願いだから早く聴かせてくれ。」
一人はまじまじとそれを眺めた。
彼にはそれが何んであるか一目見て分かった。
恐るべき名昔とでもいえば良いのだろうか。
悪魔に魂を売りわたしたといわれるあの名ヴァイオリきスト、パガニーニが愛用したとも伝えられる逸品。
これが自分の目の前にある。一人は生唾を呑み込んだ。手がかすかに震えている。
弦弓の手持ちの部分に象嵌がほどこされているのが特徴である。孔雀の目のよぅな青緑色の石が音色の気品を物語っている。
恐る恐る手に待った。
一人くらい長い間ヴァイオリンを見て来たものでも、これ程の漆黒に近い不気味な透明さを持つ名品はまず他になかった。
まさしくデーモンのようだ
一人は慎重に弦をあわせて弓をあてた。
突然一人の顔が硬張った。
弦弓を待った手かピタリと止った。目は閉じられ、左手を四本の糸に触れたまま、まるで死んだように動かない。
すると弦を押きえていた指の聞から血がしたたり落ちた。
次の瞬間、一人は狂ったように四本の弦を引きちぎった。
一人の片方の手に無残にも弦が切れたたれさがったヴァイオリンが凍りついたま
まぶらさがっている。サロメの生首のよぅにヴァイオリンの肌に一人の指の血が浸みこんでいく。
誰れもが声をあげそうになった。しかし、あまりの凄絶さにそれが声にならなかった。
「なんて事をするんだ……。」
震える声でようやく尚彦が喋った。
「なぜ、こんなものを引かせるんですか。木が腐って使いものにならない。」
「なんとか直せないのか。」
「兄さん、確かにこれは見かけだけは均整のとれた美しい形をしたヴァイオリンです。こんな名器は今まで見たことがない。でも……。」 、
「でも、何んだ。」
「芯が完全に腐っている。音色がすべて狂っているんだ。」
「それでも何も弦を切ることはないだろぅ。こんな大変な物を壊してお前はただですむと思っているのか。」
尚彦は怒りで顔が赤くなるのもかまはず怒鳴った。
「こうしなければ、又、誰かがこんむなつまらない悪戯に心を痛めるからです。演奏者を、いや音楽を冒涜するものです。」
一人は怒りの目を来栖に向けた。今まで見せたことのない程の怒りの炎が燃え広がった。
「こんな事をさせるために、僕を呼んだのですか。あなたなら分かっていたはずだ。このヴァイオリンが狂っている事を。
あなたは僕の魂を売ろうとしている。もしあなたの命ずるままにこのヴァイオリンを引いていたら、おそらく僕は一生本物の音を聴くことはできなくなったでしょう。
ぁなたは僕を罠にかけようとした。」
来栖は黙って一人の話を聴いていた。
「あなたは何を考えているんですか。僕をここに呼んで何を企もうと思ったのですか。」
「何もない。本当に苦しかっただけだ。それだけは事実だ。」
喉の奥で絞り出すように来栖は枯れた声で言った。
「僕には何かが分かりかけて果ている。ぁなたが何を企んでいるのか――。」
一人は目に涙がたまってくるのかわかった。無性に浮び上ってくるのを抑えられなかった。
「ここは、まるで邪宗の館のようだ。兄さん、早くここを出た方が良い。もうあなたには会いたくない。」
一人は館を飛び出した。
何処を走っているのかまるで見当がつかない。闇夜だけが広がっていた。
来栖に飲まされた酒がきいたのか意識が途切れ途切れになくなって行く。
朦朧とした中に、繰り返し来栖と尚彦が現われては消えた。
山科の里は夜になると人も途絶え、人家の灯もまばらだった。
一人は道を間違えて山の奥に入り込んだ。星空が美しく流れて闇に吸い込まれて行く。
冷たい風が一人の頬を打った。
闇の中に螢の光が見えた。
なんて美しいんだ……。
一人はその一つを掴もうと手を伸ばした。
彼の記憶はそこで途絶えた――。
不倫
この夏の始まりはいつになく早い。庭の草が狂ったように生えてくる。
公成は庭師をいつもより早く庭に入れて手入れをさせた。それでも雑草だけが早く伸びて彼の気持ちをざわつかせた。
そんなある日、公成は一人の事故のことを秘かに知らされた。
山科の在の溜池に溺死寸前で見つけられたと開いて、いやなものが胸にこみ上ってくるのを覚えた。
地元の警察はなかば意識不明の状態であるため身元か割り出せなかったらしい。ただ時々、詭言のように公成の名が出たのでとりあえず知らせたということらしかった。
公成の名は京都近辺では名高いので、そこら辺も配慮されたのか、新開ざたにならずに隠密にされた。
初めは自殺を疑われた。というのは崖の上にヴァイオリンか転っていたからであった。
しかし、病院で調べたところある種の薬物反応があり、それか麻薬の種類である疑いがもたれたことか警察を訝らせた。
公成は事が大きくならないうちにとすぐに手をうち、すべてを内密にさせるよ
う処理させた。
幸いにも肉体はしばらくすれば回復するとのことであった。
一人は三日後に意識を取り戻した。
彼はなぜ自分がここにいるかかはつきり分からなかった。無性に頭が痛く強い洒でも飲んだように吐気がした。
しかし、しばらくたってようやく自分の数日前の行動を思いだした。が、まだ頭が混乱してどこから考え始めてよいか分からなかった。
せめて叔父の公成に見つけられたことだけが救いであった。
公成は一人の身のまわりの世話をする者を雇っただけで、それ以上一人の身上については聞こうとはしなかった。
が、その叔父の気持ちが分るだけに、口を閉ざして何も語らない自分の我が儘に苦しんだ。
「ご迷惑をかけてすみません。」
ある日、公成が見舞いに釆た時に一人はようやく口を開いた。
「なに、気にすることはないさ。わしもぉ前ぐらいの時にはいろいろとムチャをしたからな。」
「東京には知らせたのですか。」
「いや……。」
「たださぐりを入れてみた。案の定、筥子が出て、口止めされているけれどという事で、話しはしてくれたがな。」
公成は遠くを眺めた。自分の普にもこんな事があったような気がした。若い頃のことは彼にとっては想い出す事も残っていなかった。
「筥子はお前がひょつとしたらわしの所に居ることを知っているかもしれないな。
それとなく蓮司について京都に来ているようだ。」
「そうですか、心配をかけてるな。父のことは何か言ってませんでしたか。」
一人はそれが一番気がかりだった。自分をあんなに可愛がってくれた父を裏切
って飛び出して釆たことをひどく後悔した。
「いや、なんとも言ってなかったな。まあ、あれのことだからずいぶん怒ったろうがな。
しかし、お前ももう二十歳にもなるし、今さら自分の手の中に入れてもおけない
だろうがな。」
公成は話をはぐらかした。
筥子から艸人のことを開かされて、それで頭の中が澱んでいた。
ほとんど一日中部屋に籠っているとは普通じゃない……。
普、一人がイタリアに留学する時にもあれこれと気をもんでいたのは知っていたが、こうまで溺愛しているとは――。公成は内心、兄の偏愛ぶりに驚かされた。
歳をとったのかな――。
公成は兄の弱り方を見て嘆息した。
老いが始っている。やがてそれは自分にも来るのだろうか。
そう考えると無性に若い頃が想い出された。彼らしからぬ迷いが頭をよぎつた。
「ここに居ることは誰れも知らん。お前のことは当分秘密にしておこう。」
「何も話せなくて申しわけありません。」
「別に聞こうとも思わん。そのうち話したくなったらいつでも家の方に来い。だが、しばらくして落着いたら手紙だけは出しておけよ。少しは気が楽になるだろう。」
「そうします……。」
一人は蒼い顔を曇らせた。
「何処かでゆっくり考えてはどうだ。」
「今は何処にも行くあてもありません。」
「わしが良い処を知っている。そこで静養しながら身の振り方を考えるんだな。」
この子は何を隠しているのだろう…。
公成は一人の顔を見つめながら不思議に思った。
今まであんなに素直な青年であったのに心が曇っている。
いや、この子ばかりでなく室生家のすべてがゆっくり奈落の底に沈み込んで行く光景が浮んだ。
耳を裂くような啼き声が聞こえた。どこかの鳥が暑さに耐えかねて鋭い声を張りあげたのだろうか。
しかし、公成には自分の家の床間に替けてある孔雀明王の絵が啼いているような気がした。
彼は多くの名品を持っているが、その中でもこの大幅の絹本仏画を守護仏として日夜析頑していた。
じっとこちらを見つめる青緑色の孔雀の上に蓮華と孔雀の羽を両手に待った明王がのっている。そのまわりには黄金の羽が鏤められている。値段のつけようもない逸品である。
彼は祈ることにより、精神の汚れが浄められるような気になるのであった。
その孔雀が狂ったように啼いている。
なんの前ぶれなのだろう。
彼は軽い立ちくらみを覚えた。
公成の暗い気分を一人はもちろん知る由もなかった――。
しばらくして、公成は所用で神戸まで出向いた。
その夜は六甲の麓にある別邸に泊まることにした。
彼がここに泊まるのには実はもっと別の理由があった。公成は京都と大津にお気入りの庵を持っている。
一代の数寄者らしく、その土地土地の地形を巧みに利用して実に見事な借景をみせる庵を自慢している。京の家は華麗で、大津はひなびた面影があった。彼はきまって大茶会を大津の庵で催した。
何百人もの茶人を招いて開く茶会などは豪商の多い京都でも近頃ではめったに開かれない。公成はそれを一番自慢していた。
しかし、大津の茶会が表の楽しみであるならば、この六甲の家は裏のひそかな楽しみのために造られたものだった。
ごく親しいものでさえ、その在りかを知らない。いや、そこに公成が家を持っていることさえ噂にものばらない。
その家はいわば高級旅館であった。人の目を避けて逢い引きをしなければならない男女のための特別の工夫をこらして造られた場所であった。
公成は月のうち何度かそこで過ごすことにしている。
裏の木戸を押すと誰れにも見られずに彼の部屋に入れる。ここに居る時がもっとも自由な気分になる。
京にいる時には名士として見られ、大津にいる時には数寄者と呼ばれる。時にそれが煩わしくなることがある。
もっと赤裸々に生を取り戻したい欲望が彼を苛むのだった。
その意味でこの家は自由だった。誰れと会うわけでもなく、何ものにも拘束されず、ここの使用人にさえ彼がいつこの部屋を使っているのかが分からない。
木造りの何もない部屋で彼はまったく生(き)のままの自分を見つけるのだった。
彼のもう一つの楽しみは隣り部屡にあった。すぐ扉の向こう側では、この旅館にしけこんだ男女の愛の行為が日夜繰り返される享楽の部屋がある。
彼の部屋とその密室の間にはほんの小さな覗き窓がある。
彼の楽しみはそこにあった。
小さな藁瓶から白い錠剤を取りだして口に含む。かなり強い催淫剤である。以前にある中国の貿易商より分けてもらったその薬のおかげで精力をたもたせていた。
口の中でとろりとした乳白色の液体になると頭の芯が微かに熱をおぴてくる。
ようやく喝きが襲ってきた。
彼はうつろに韓の部屋を覗く。若い男女の淫らな声が聞こえてくる。
男と女の寝室のまじわりをじっと眺めている。そうやって飽きずに繰り返し絶頂に達する女の声を開くのが最高の快楽
だった。
そんな時、彼はひどく自分が無心になれるのが不思議に思われるのだった。
ここに釆て一時の快楽に溺れる男と女、そしてその行為を眺める好色な老人……。
およそ人の欲望ほどどす黒く、奥深いものはない ー 。
公成は開の中で苦笑いを殺した。
ふくよかな女だった。
歯並びの良い色白の若い女を彼は好んだ。部屋が薄暗いので、女がどんな顔をしているかまでは分からなかった。
ただ、女の荒い息づかいが性への欲望を躯ごと表現しているようで妙になまめかしい。
どうやら自分も目が悪くなってきた。昔は遠くの鳥の種類さえ見分けられたものだが……。
公成は目をこすって暗闇の男女の顔を見ようとした。
カタッと背中で音がした。
何処から入って釆たのか、そこにはたくましい若者が座していた。
公成が日頃、秘密の仕事をまかせるために使う男であった。
「お呼びでしょうか。」
「また仕事だ。」
「株の方でしょうか。それとも……。」
「いや、そんな事じゃない。ちょっとした調べごとをしてほしい。」
「調査ですか、それでしたら私くしでなくてもよろしいでしょう。」
「いやお前が良い。お前じゃなければできんだろう。」
公成は隣の部屋の男女の痴態から目を放さないまま低く笑った。
「ある男を詞べるんだ。」
「男……。」
「名前をあげれば、お前の頭の中にも顔ぐらいは浮ぶだろう。」
「それでその男の何を詞ペましょうか。」
男は無表情に聞き返した。
「こころだよ。」
「こころ?」
「そう心だ。その男が何を考えているか、わしには興味があるんだ。なるべく早く動くんだ。」
「わかりました。名前はなんと言うのでしょうか。」
「来栖、来栖瓏だよ。」
男の口唇が何かを言いかけて止めた。
深々と額を床につくまで曲げて一礼をすると音もなく部屋を出て行った。
公成は薬のおかげで次第に意識が遠のいて行くのが分かった。
女の白い喉が見えた。形の良い口唇が悦びの声をもらした。
「ほほ、つ、なかなか形の良い歯をしている」
公成はほくそえんだ。
が、次の瞬間、その実いは・凍りついた。
「筥子′こ
口の中で言葉が破裂した。
自分の頭が狂ったのだろうか。
なぜここに筥子が――。
彼は自分が錯乱しているとしか思えなかった。
赤い蒲団を握りしめて恍惚の表情で獣のように男の背中に爪をたてている女
それは筥子に違いなかった。
まさか……。
公成にはもう何が目の前で起きているのかが判然としなかった。膝がガタガタと震えて立っていることが出来ない。
顔からは血の気が失せ、口唇は紫色になった。
彼がそのまま床に崩れるように倒れたのは次の瞬間だった。
白い獣を抱きすくめていた長身の男の背中が夫の蓮司のものでないことはすぐ分った。
妖しい灯に昭らししだされて大きく浮かび上った背中を見て公成は失神した。
それは彼が小さい時から育てて来た男の遥しく成長した後姿にあまりに酷していたのである。
戻る 続く
「見てごらん。」
来栖はバルコニーの上から浴場の青年たちを指さした。
浴場といってもそこは一種のトレーニングルームを兼ねているジムであった。ただ一面大理石で磨かれていることが一人には不思議に思われた。
床の小さな穴から水蒸気が吹きだして青年たちの裸身を隠している。
彼らはそれぞれかってに自由な運勤をしながら躯を鍛えている。
汗がふきだして胸が朱に染った青年がサウナから飛び出すと思いきってプールの中に身をおどらせた。
歓声が起った。
浴場の丁度まん中で一組の青年がレスリングをしている。互いに力が互角らしくなかなか技がきまらない。
まるで二匹の牡鹿が角を競いあっているような光景である。
一人は青年の小麦色に輝いたたくましい肌に思わず見とれた。均整のとれた肉体が飛びはねている姿はそのまま舞踏のように白い軌跡を描いては消えていく。
美しい、一人はしばらく彼らに見蕩れてしまった。
「あの人たちは護れなのですか。」
一人は自分の白い肌を思い浮べて困惑しながら訊ねた。
「みんな俺の弟子たちだ。役者もいれば舞踏家もいる。素晴しいとは思わないかね。ここでこうして躯を鍛えさせて、自分を芸術にする。肉体がこんなにも美しくなることを誰れが想像したろう。」
来栖はうっとりとした目で青年を眺めた。彼らはまったく伸び伸びと自分の肉体を磨き上げることに耽溺していた。
まるで彫刻のようだ。
一人は野外庭園に迷い込んだ時の事を思い出した。道の並木に平行して幾体もの彫像がならべられていた。彼はその下をくぐりぬけながら本当にこれが人間の躯なのだろうか、といぶかしんだ。
だが、目の前の男たちの躯はまさしくその悪魔を払いのけるのに十分に完壁だった。
まさしく神が作り上げた傑作が目の前にあるのだ。
一人は嘆息をついた。
「青年の肉体は一つの芸術だよ。美しい神秘なんだ。それに比べれば女の躯など安物でつまらないものだ。」
一人は瓏の顔を見つめた。純粋な瞳の輝きが一瞬、残酷な光をおぴて獲物を傷つける刃を映した。
一人は寒気におそわれた。ここから逃げ出したかった。
が、そうするのができないのはやはり瓏の心の奥に何か一人がのぞきこめない情熱があるような気がするからであった
それが何んなのか、判らない。
この人には何かが隠されている。
運命の残忍さを一人は予感していた。自分ばかりでなく、まわりの愛情ある人たちもすべて切り裂いてしまうようなひどく辛い運命が待っている。
しかし、今の彼には瓏の心の邪悪な愛情に逆に引かれるのであった。
この人の仮面の奥にはどんな顔が隠されているのだろう。
一人はそれを知りたくてここに来たのを忘れてしまっていた。
「あれを見てごらん。」
物思いに沈んでいた一人に来栖が声かけた。
「あの青年を知っているだろう。」
部屋のまん中にいる美貌の青年を指差した。
蒸せた湯気ではっきりしなかったが先程の組み撃ちをしていた青年らしく、相手を倒した歓声に囲まれていた。
勝者の祝杯だろうか、銀色のリュトンを高く挙げた青年の顔が見えた。
一人は思わず息を呑んだ。
「兄さん!」
叫び声が壁にこだまして響きわたった。
浴場の青年たちが一斉にバルコニーを見上げた。青年の目が一人を捉えた。
「一人……」
青年は呆然と立ちすくんだ。
どうして弟がここに来ているんだ。それよりも自分の淫らな婆を見られたこに当惑した。
兄弟はしばらく無言のまま見つめあった。まわりの者は好奇の目で眺めていだが、来栖の視線だけは冷静に二人の若者そそがれていた。醒めて邪悪な光がその中に宿っている。
どうやって尚彦に声をかければよいのだろうか。一人はためらった。
彼を驚かせたのは尚彦の裸の胸に緑と青で刺青させたエクウスの頭首であった。
今にも飛び出さんばかりに目をむいたエクウスが熱気で灼けた肌にたて髪をなびかせている。
「兄さん、その刺青はどうしたの。」
一人はじっとそれを見つめた。線の刺し方からかなりの腕の職人の仕事であることは分かった。胸から腹にかけて一息に彩られた生々しさがまるで生物のように波うっている。
「そんな余計な事はどうでもいい。それよりも、お前はなぜここにいるんだ。」
一人は答えに詰った。自分でもここに居る理由が解からなかった。
まわりの青年たちの好奇の目が一人にそそがれた。彼だけが服を着けていることが、ひどく恥かしいように思われた。あから様に彼を見くだす者もいた。
ここはお前のような青白い小僧が来る所じゃないぞとさも言いたげな視線である。
あるいは瓏の新しい恋の相手だとでも思ったのだろうか、冷たい刺すような視線が痛いほど分かった。
「一人は俺が呼んだんだよ。」
来栖が重たい口を開いた。
一瞬、尚彦の顔が青ざめた。血の気が失せていまにも倒れそうであった。
この様な兄のあられもない姿を見るの一人はしのぴなかった。
確かに一人は来栖にあこがれていた。丁度青年が麗人にあこがれるような、ほのかな恋心に近い気持ちだった。
しかし、兄のような何もかも言うがままの恋ではなかった。
これではまるでハーレムではないか――。
なぜ兄はこんな事をしてまで来栖に従っていなければならないのだろう。
先程まであんなに美しく見えた青年たちの裸身がロボットのような金属的な味けないものに写った。
わけの分からない怒りが一人の裸にこみ上げて来た。
「どうしようもなく苦しくなって、彼を呼んだんだよ。]
「一人を呼んで何をしようというんですか。」
尚彦はヒステリッタに叫んだ。
「ヴァイオリンを聴きたかった。俺の心には一人のひく曲が必要なんだ。」
来栖はとぼけたように答えた。
「兄さん、その刺青は何?」
ようやく落着いた一人が訊ねた。
「悪戯だよ。冗談にやったのさ。ここにもう一つある。」
と言って尚彦は左手の甲を一人に示した。
真紅の薔薇が一輪描かれていた。
「尚彦に刺青をしたのはこの俺だ。]
「あなたが……。」
「そうだ。俺の命じたままに馬の刺青をしたんだ。」
「何んでそんなことをしたの。父さんに知れたら大変なことになるのに。」
「ハハハハ」
来栖は高らかに笑った。それにつれてどっと笑い声が起った。
「君はまるで少年のようだ。」
来栖は口唇をなめながら一人を見た。
「もっともその美しい瞳が俺を狂わせるのだが……。」
「一人、ここはお前の来る所ではない。早く帰れ。ここは役者の修業の場所なんだ。毎日が血の出るような開いの場所だ。
ここに入れてもらうことでさえ大変な
名誉なことなんだ。」
「役者の勉強だけじゃないがな。」
遠くで誰れかがからかった。またしても爆笑が起った。
「俺はここに居て、すごく自分の生きがいを感じている。躯のあらゆる所に力がみなぎつている。不思議に刺青をしてから自分の思うように躯が動くんだ。」
「ぼくにはそう思えない。兄さんは無理をしている。昔のようにぼくを正面から見れなくなっている。兄さんは間違っているよ。」
一人は鋭い声で兄に言った。
今まで浴場に漂っていた熱気がいつの間にか引いて底寒くなった。
尚彦の顔が怒りでみるみる紅潮した。興奮して今にも一人に殴りかかろうとした。
来栖は相かわらず冷静に二人を見つめていた。
まるで兄弟の争いを予見したかのように、巧みに操っているような目つきであった。
尚彦の一撃が一人の頬をまさに打たんとした。
その瞬間、尚彦の手は空中で静止した。荒々しい挙がしっかりと後ろから掴まれた。
来栖は尚彦の手を突き放した。その反動でよろめいた彼の右手には赤く痣ができて腫れあがっていた。
「弟の手をあげるとは感心しないね。見ろ、お前のとんでもない余興で風呂が冷えてしまった。お前の躯を見ろ。まるで羽をむしられた鳥のようだ。」
尚彦は首を垂れたまま黙った。
「一人君、ぴっくりさせてすまなかった。最初から君に話しておけば良かったが、尚彦は俺があづかっている。役者にする為には少し荒修業もしなくてはならない。
ここにいる時は誰れの干渉もうけない。
例え君であってもだ。」
一人は来栖の凛とした声に次第に冷静さをとりもどした。
「それよりも、君にこれを使って演奏してほしいんだ。」
彼は一人の前に一丁の黒ニスで塗られたヴァイオリンを置いた。
「このヴァイオリンを君に引いてもらうのを俺は夢にまで見ていた。何度も同じ夢を見て苦しんだ。さあ、お願いだから早く聴かせてくれ。」
一人はまじまじとそれを眺めた。
彼にはそれが何んであるか一目見て分かった。
恐るべき名昔とでもいえば良いのだろうか。
悪魔に魂を売りわたしたといわれるあの名ヴァイオリきスト、パガニーニが愛用したとも伝えられる逸品。
これが自分の目の前にある。一人は生唾を呑み込んだ。手がかすかに震えている。
弦弓の手持ちの部分に象嵌がほどこされているのが特徴である。孔雀の目のよぅな青緑色の石が音色の気品を物語っている。
恐る恐る手に待った。
一人くらい長い間ヴァイオリンを見て来たものでも、これ程の漆黒に近い不気味な透明さを持つ名品はまず他になかった。
まさしくデーモンのようだ
一人は慎重に弦をあわせて弓をあてた。
突然一人の顔が硬張った。
弦弓を待った手かピタリと止った。目は閉じられ、左手を四本の糸に触れたまま、まるで死んだように動かない。
すると弦を押きえていた指の聞から血がしたたり落ちた。
次の瞬間、一人は狂ったように四本の弦を引きちぎった。
一人の片方の手に無残にも弦が切れたたれさがったヴァイオリンが凍りついたま
まぶらさがっている。サロメの生首のよぅにヴァイオリンの肌に一人の指の血が浸みこんでいく。
誰れもが声をあげそうになった。しかし、あまりの凄絶さにそれが声にならなかった。
「なんて事をするんだ……。」
震える声でようやく尚彦が喋った。
「なぜ、こんなものを引かせるんですか。木が腐って使いものにならない。」
「なんとか直せないのか。」
「兄さん、確かにこれは見かけだけは均整のとれた美しい形をしたヴァイオリンです。こんな名器は今まで見たことがない。でも……。」 、
「でも、何んだ。」
「芯が完全に腐っている。音色がすべて狂っているんだ。」
「それでも何も弦を切ることはないだろぅ。こんな大変な物を壊してお前はただですむと思っているのか。」
尚彦は怒りで顔が赤くなるのもかまはず怒鳴った。
「こうしなければ、又、誰かがこんむなつまらない悪戯に心を痛めるからです。演奏者を、いや音楽を冒涜するものです。」
一人は怒りの目を来栖に向けた。今まで見せたことのない程の怒りの炎が燃え広がった。
「こんな事をさせるために、僕を呼んだのですか。あなたなら分かっていたはずだ。このヴァイオリンが狂っている事を。
あなたは僕の魂を売ろうとしている。もしあなたの命ずるままにこのヴァイオリンを引いていたら、おそらく僕は一生本物の音を聴くことはできなくなったでしょう。
ぁなたは僕を罠にかけようとした。」
来栖は黙って一人の話を聴いていた。
「あなたは何を考えているんですか。僕をここに呼んで何を企もうと思ったのですか。」
「何もない。本当に苦しかっただけだ。それだけは事実だ。」
喉の奥で絞り出すように来栖は枯れた声で言った。
「僕には何かが分かりかけて果ている。ぁなたが何を企んでいるのか――。」
一人は目に涙がたまってくるのかわかった。無性に浮び上ってくるのを抑えられなかった。
「ここは、まるで邪宗の館のようだ。兄さん、早くここを出た方が良い。もうあなたには会いたくない。」
一人は館を飛び出した。
何処を走っているのかまるで見当がつかない。闇夜だけが広がっていた。
来栖に飲まされた酒がきいたのか意識が途切れ途切れになくなって行く。
朦朧とした中に、繰り返し来栖と尚彦が現われては消えた。
山科の里は夜になると人も途絶え、人家の灯もまばらだった。
一人は道を間違えて山の奥に入り込んだ。星空が美しく流れて闇に吸い込まれて行く。
冷たい風が一人の頬を打った。
闇の中に螢の光が見えた。
なんて美しいんだ……。
一人はその一つを掴もうと手を伸ばした。
彼の記憶はそこで途絶えた――。
不倫
この夏の始まりはいつになく早い。庭の草が狂ったように生えてくる。
公成は庭師をいつもより早く庭に入れて手入れをさせた。それでも雑草だけが早く伸びて彼の気持ちをざわつかせた。
そんなある日、公成は一人の事故のことを秘かに知らされた。
山科の在の溜池に溺死寸前で見つけられたと開いて、いやなものが胸にこみ上ってくるのを覚えた。
地元の警察はなかば意識不明の状態であるため身元か割り出せなかったらしい。ただ時々、詭言のように公成の名が出たのでとりあえず知らせたということらしかった。
公成の名は京都近辺では名高いので、そこら辺も配慮されたのか、新開ざたにならずに隠密にされた。
初めは自殺を疑われた。というのは崖の上にヴァイオリンか転っていたからであった。
しかし、病院で調べたところある種の薬物反応があり、それか麻薬の種類である疑いがもたれたことか警察を訝らせた。
公成は事が大きくならないうちにとすぐに手をうち、すべてを内密にさせるよ
う処理させた。
幸いにも肉体はしばらくすれば回復するとのことであった。
一人は三日後に意識を取り戻した。
彼はなぜ自分がここにいるかかはつきり分からなかった。無性に頭が痛く強い洒でも飲んだように吐気がした。
しかし、しばらくたってようやく自分の数日前の行動を思いだした。が、まだ頭が混乱してどこから考え始めてよいか分からなかった。
せめて叔父の公成に見つけられたことだけが救いであった。
公成は一人の身のまわりの世話をする者を雇っただけで、それ以上一人の身上については聞こうとはしなかった。
が、その叔父の気持ちが分るだけに、口を閉ざして何も語らない自分の我が儘に苦しんだ。
「ご迷惑をかけてすみません。」
ある日、公成が見舞いに釆た時に一人はようやく口を開いた。
「なに、気にすることはないさ。わしもぉ前ぐらいの時にはいろいろとムチャをしたからな。」
「東京には知らせたのですか。」
「いや……。」
「たださぐりを入れてみた。案の定、筥子が出て、口止めされているけれどという事で、話しはしてくれたがな。」
公成は遠くを眺めた。自分の普にもこんな事があったような気がした。若い頃のことは彼にとっては想い出す事も残っていなかった。
「筥子はお前がひょつとしたらわしの所に居ることを知っているかもしれないな。
それとなく蓮司について京都に来ているようだ。」
「そうですか、心配をかけてるな。父のことは何か言ってませんでしたか。」
一人はそれが一番気がかりだった。自分をあんなに可愛がってくれた父を裏切
って飛び出して釆たことをひどく後悔した。
「いや、なんとも言ってなかったな。まあ、あれのことだからずいぶん怒ったろうがな。
しかし、お前ももう二十歳にもなるし、今さら自分の手の中に入れてもおけない
だろうがな。」
公成は話をはぐらかした。
筥子から艸人のことを開かされて、それで頭の中が澱んでいた。
ほとんど一日中部屋に籠っているとは普通じゃない……。
普、一人がイタリアに留学する時にもあれこれと気をもんでいたのは知っていたが、こうまで溺愛しているとは――。公成は内心、兄の偏愛ぶりに驚かされた。
歳をとったのかな――。
公成は兄の弱り方を見て嘆息した。
老いが始っている。やがてそれは自分にも来るのだろうか。
そう考えると無性に若い頃が想い出された。彼らしからぬ迷いが頭をよぎつた。
「ここに居ることは誰れも知らん。お前のことは当分秘密にしておこう。」
「何も話せなくて申しわけありません。」
「別に聞こうとも思わん。そのうち話したくなったらいつでも家の方に来い。だが、しばらくして落着いたら手紙だけは出しておけよ。少しは気が楽になるだろう。」
「そうします……。」
一人は蒼い顔を曇らせた。
「何処かでゆっくり考えてはどうだ。」
「今は何処にも行くあてもありません。」
「わしが良い処を知っている。そこで静養しながら身の振り方を考えるんだな。」
この子は何を隠しているのだろう…。
公成は一人の顔を見つめながら不思議に思った。
今まであんなに素直な青年であったのに心が曇っている。
いや、この子ばかりでなく室生家のすべてがゆっくり奈落の底に沈み込んで行く光景が浮んだ。
耳を裂くような啼き声が聞こえた。どこかの鳥が暑さに耐えかねて鋭い声を張りあげたのだろうか。
しかし、公成には自分の家の床間に替けてある孔雀明王の絵が啼いているような気がした。
彼は多くの名品を持っているが、その中でもこの大幅の絹本仏画を守護仏として日夜析頑していた。
じっとこちらを見つめる青緑色の孔雀の上に蓮華と孔雀の羽を両手に待った明王がのっている。そのまわりには黄金の羽が鏤められている。値段のつけようもない逸品である。
彼は祈ることにより、精神の汚れが浄められるような気になるのであった。
その孔雀が狂ったように啼いている。
なんの前ぶれなのだろう。
彼は軽い立ちくらみを覚えた。
公成の暗い気分を一人はもちろん知る由もなかった――。
しばらくして、公成は所用で神戸まで出向いた。
その夜は六甲の麓にある別邸に泊まることにした。
彼がここに泊まるのには実はもっと別の理由があった。公成は京都と大津にお気入りの庵を持っている。
一代の数寄者らしく、その土地土地の地形を巧みに利用して実に見事な借景をみせる庵を自慢している。京の家は華麗で、大津はひなびた面影があった。彼はきまって大茶会を大津の庵で催した。
何百人もの茶人を招いて開く茶会などは豪商の多い京都でも近頃ではめったに開かれない。公成はそれを一番自慢していた。
しかし、大津の茶会が表の楽しみであるならば、この六甲の家は裏のひそかな楽しみのために造られたものだった。
ごく親しいものでさえ、その在りかを知らない。いや、そこに公成が家を持っていることさえ噂にものばらない。
その家はいわば高級旅館であった。人の目を避けて逢い引きをしなければならない男女のための特別の工夫をこらして造られた場所であった。
公成は月のうち何度かそこで過ごすことにしている。
裏の木戸を押すと誰れにも見られずに彼の部屋に入れる。ここに居る時がもっとも自由な気分になる。
京にいる時には名士として見られ、大津にいる時には数寄者と呼ばれる。時にそれが煩わしくなることがある。
もっと赤裸々に生を取り戻したい欲望が彼を苛むのだった。
その意味でこの家は自由だった。誰れと会うわけでもなく、何ものにも拘束されず、ここの使用人にさえ彼がいつこの部屋を使っているのかが分からない。
木造りの何もない部屋で彼はまったく生(き)のままの自分を見つけるのだった。
彼のもう一つの楽しみは隣り部屡にあった。すぐ扉の向こう側では、この旅館にしけこんだ男女の愛の行為が日夜繰り返される享楽の部屋がある。
彼の部屋とその密室の間にはほんの小さな覗き窓がある。
彼の楽しみはそこにあった。
小さな藁瓶から白い錠剤を取りだして口に含む。かなり強い催淫剤である。以前にある中国の貿易商より分けてもらったその薬のおかげで精力をたもたせていた。
口の中でとろりとした乳白色の液体になると頭の芯が微かに熱をおぴてくる。
ようやく喝きが襲ってきた。
彼はうつろに韓の部屋を覗く。若い男女の淫らな声が聞こえてくる。
男と女の寝室のまじわりをじっと眺めている。そうやって飽きずに繰り返し絶頂に達する女の声を開くのが最高の快楽
だった。
そんな時、彼はひどく自分が無心になれるのが不思議に思われるのだった。
ここに釆て一時の快楽に溺れる男と女、そしてその行為を眺める好色な老人……。
およそ人の欲望ほどどす黒く、奥深いものはない ー 。
公成は開の中で苦笑いを殺した。
ふくよかな女だった。
歯並びの良い色白の若い女を彼は好んだ。部屋が薄暗いので、女がどんな顔をしているかまでは分からなかった。
ただ、女の荒い息づかいが性への欲望を躯ごと表現しているようで妙になまめかしい。
どうやら自分も目が悪くなってきた。昔は遠くの鳥の種類さえ見分けられたものだが……。
公成は目をこすって暗闇の男女の顔を見ようとした。
カタッと背中で音がした。
何処から入って釆たのか、そこにはたくましい若者が座していた。
公成が日頃、秘密の仕事をまかせるために使う男であった。
「お呼びでしょうか。」
「また仕事だ。」
「株の方でしょうか。それとも……。」
「いや、そんな事じゃない。ちょっとした調べごとをしてほしい。」
「調査ですか、それでしたら私くしでなくてもよろしいでしょう。」
「いやお前が良い。お前じゃなければできんだろう。」
公成は隣の部屋の男女の痴態から目を放さないまま低く笑った。
「ある男を詞べるんだ。」
「男……。」
「名前をあげれば、お前の頭の中にも顔ぐらいは浮ぶだろう。」
「それでその男の何を詞ペましょうか。」
男は無表情に聞き返した。
「こころだよ。」
「こころ?」
「そう心だ。その男が何を考えているか、わしには興味があるんだ。なるべく早く動くんだ。」
「わかりました。名前はなんと言うのでしょうか。」
「来栖、来栖瓏だよ。」
男の口唇が何かを言いかけて止めた。
深々と額を床につくまで曲げて一礼をすると音もなく部屋を出て行った。
公成は薬のおかげで次第に意識が遠のいて行くのが分かった。
女の白い喉が見えた。形の良い口唇が悦びの声をもらした。
「ほほ、つ、なかなか形の良い歯をしている」
公成はほくそえんだ。
が、次の瞬間、その実いは・凍りついた。
「筥子′こ
口の中で言葉が破裂した。
自分の頭が狂ったのだろうか。
なぜここに筥子が――。
彼は自分が錯乱しているとしか思えなかった。
赤い蒲団を握りしめて恍惚の表情で獣のように男の背中に爪をたてている女
それは筥子に違いなかった。
まさか……。
公成にはもう何が目の前で起きているのかが判然としなかった。膝がガタガタと震えて立っていることが出来ない。
顔からは血の気が失せ、口唇は紫色になった。
彼がそのまま床に崩れるように倒れたのは次の瞬間だった。
白い獣を抱きすくめていた長身の男の背中が夫の蓮司のものでないことはすぐ分った。
妖しい灯に昭らししだされて大きく浮かび上った背中を見て公成は失神した。
それは彼が小さい時から育てて来た男の遥しく成長した後姿にあまりに酷していたのである。
戻る 続く