蕁草の園(2)
中村祐之
イラスト・山口喜造
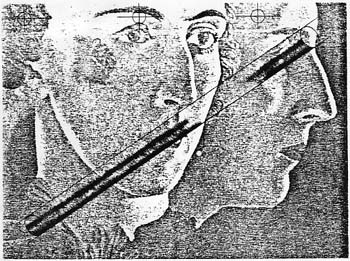
修羅の舞台
漆黒の闇だった。
あたり一面を覆う暗闇が、一瞬にして観客を沈黙させた。鼻をつく闇とはおそらくこの事をさすのだろう。空も大地もなくあらゆる人の目の届く限り壁のような闇であった。
ほんの少し前、舞台は燦然と輝く陽の光を浴びて緋色に染った。
天を翔ける金色の髪毛を長く書かせた
勇者ぺレーロポンテースが、愛馬とともに天まで登ろうとした。
その一瞬、主神ゼウスの怒りに触れたぺレーロポンテースは失墜して燃えた。
突然、轟音がとどろき、舞台は赤く燃えた。目を潰す眩しさに観客は思わず手をかざした。
青年の燃えて行く様は、まるで炎の鳥のように美しく、火の尾羽を長くひきながら弧を描いて地に堕ちた。
青い瞳が燃え上り、珊瑚のように美しい口唇に火がつき、髪毛が輝いた。小さな叫びを残して青年は奔馬とともに奈落に消えていった。
人々は闇の海に取り残された。
しばしの深い静寂の中で、先程の美の主人公の余韻を楽しんだ。そして、ようやくこの大作「ぺレーロポンテース」が終曲になったことを悟った。
音楽だけが、闇の中で響く。
深い藍、さめるような青い色を思わせる音。水の中を漂うように、躯がふわりと浮び上がる。
が、闇の中で二つの目だけが冷たく光っていた。
おそらく、この舞台のどのライトよりも強く役者の動きをひとつひとつくさすように見つめる目。醒めている瞳の奥で、炎が燃え上っていた。
恐しい程の眼差。張りのある瞳。
この眼差しで見つめられたら、どんな獰猛な獣でさえ怖気づいてしまうことだろう、と演出の助手たちはいつも思うのである。しかし、来栖瓏という演出家に付いていられるだけでも彼らは満足していた。
彼らは、この若くして国際的な名声を博している演出家の秘技に少しでもあやかろうと、先を争って助手を志願した。と同時に、あまりのスケールの大きさに肝をぬかして、立ち去っていく者が後を絶たなかった。
確かに、このエネルギイッシュな演出家にあわせようとしたならば、おそらく並の神経では勤まらないだろう。
彼は常に動いていた。
動くことによって自分のイメージを創り出す。指先で指示する時には頭の中にはもう何頁か先のシークエンスが広がっている。
完全主義者であり、すべてに完成された美こそが絶対だと信ずる宗教的なファナチィストでもあった。
彼の白い爪先が瞬時に空を切った。
闇の中におばろげに二人の人物が杖をたよりに現われた。
先程の勇者の面影はまるでなく、ヨロヨロと力なく歩いてくる。煤けた顔をして、痩せこけた胸をあらわにしたペレーポンテースがスポットライトに照らし出された。
燦然と輝いて金色の髪も汚れて汗ばんでいる。彼らが歩くたびに赤茶けた砂が舞い上る。
従者であろうか年をとった男が肩をかしながら、美貌の青年を辛うじて支えていた。
「ペガソスよ。ペガソスよ。どこに居る。」
青年の弱々しいが凛とした声が響いた。
『ご主人様、ああ、おいたわしい。』
『ペガソスか、私は目をやられたらしい。何も見えない。』
『ああ、おいたわしや、ご主人様。私はここに居ります。』
『ここに、ここに居るというのは……この艶のない顔、縮れた老人の髪の毛をしたお主がそうだと言うのか。』
『そうでございます。』
『ハハハ、何を馬鹿なことを言っているのだ。』
青年の両眼から血の涙が流れた。
『どこの誰だか知らぬが救えてやろう。いいか、ペガソスというのは、すばらい戦士で、俺と一緒に連戦に連戦を重ねた。四肢の肉の良く張った屈強な奴だ。誰がお前のような老いぼれと一緒なものか
コリントスで戦った時も、そうだ、あのリユキアでの戦さの時も、俺と一緒に奮戦したものだ。疲れを知らなかった奴だ。』
『そうでございます。あなた様はあの青鷺の羽を一本右の胸にさされで出陣なさいました。それにキマイラとの戦いの最中、私を助けていただいたことがごいます。』
『コリントスで戦った時も、そうだ、あのリユキアでの戦さの時も、俺と一緒に奮戦したものだ。疲れを知らなかった奴だ。』
『そうでございます。あなた様はあの時、青鷺の羽を一本右の胸にさされて出陣なさいました。それにキマイラとの戦いの最中、私を助けていただいたことがございます。』
『キマイラとの……。』
『そうです、ご主人様。あなたのそばにずっとお仕えしておりょしたのは私でございます。
そうやって両の目が潰れて初めて、あなた様は私の本当の姿を見ることができたのです。』
『そうか、永い間俺のそばに居たのはお前であったか……。ハハハ。』
青年は痴呆のようにだらしなく笑った。
『皮肉なものだな。こうやってどことも判らない場所を彷徨いながら、俺は初めて自分を判ったような気がするぞ。』
青年はベガリスの肩から離れると、杖を片手によろけながら舞台の其ん中に進んだ。そして頭を少しばかり上けた。
またしても乾いた砂が舞い上がった。
『風が吹いているのか。お前には何か見えるか。』
『いいえ、私にも何も見えません。闇です。あなた様が見つめていられる闇よりも、まだ深い闇です。』
『そうか。もうずっと昔だ。そぅだな子供の頃に父に開かされたことがあった。こうやって頭を上につきあげて、もし風が吹いていないとしたら、そこがお前の死ぬ場所だとな。』
観客席には咳ひとつおこらなかった。
それ程までに、この劇のエピローグには予感があった。
じっと主人公の演技に目を注いでいた来栖の瞼は閉ざされていた。何かを待ちのぞんでいるかのように、じつと音楽を聴いていた。
助手たちは、閉ざされた瞳の臭で何を考えているのかを訝しんだ。劇よりももっと残忍でもつと忌しい虚無が彼を捉えていることだけは確かであった。
白い陽炎
舞台の下手でプロデューサーの福山が一人悦にいっていた。
最初、この劇に来栖が駆け出しの役者を使うといった時には、さすがに反対した。何よりも今回の劇には主役の持ち場面が多く、それだけに熟練さが要求されてくる。そんな所に何回か噂されたことがあるかも知れないにしろ、まだまだ未熟な俳優を使うことは危険が大き遺ぎた。
しかし、来栖は若い役者を強く薦した。
名を室生尚彦と言う。ようやく売りだし始めた役者であった。
福山は渋々承諾した。いくら彼が横ヤリを入れたとしても耳をかすような相手ではなかったからである。それに尚彦が高名な戯曲家の艸人の息子ということも、少なからず彼の計算の中にはあった。
『まあ、やらせてみるとするか。』
彼の裡にはすでに次のプランがあった。前からこの老大家の戯曲をどうしても手掛けたかった。もうすぐでき上る国立オペラ劇場の柿(こけら)落しでその戯曲を上演したかったのである。
だから、少々危険な賭であるが尚彦を主役に抜述するにはやぶさかではなかった。
『それにしても……。』
福山は一人でほくそ笑んだ。これ程までに尚彦が力強い演技を見せるとは思わなかった。
「ハガネのような躯だ」と、栗栖がもらしたことがあったが、やはり血筋が良いのだろうか、正直なところ福山も舌を巻いた。けっして躊躇するところがない。若さというのはこうも人を神がかりにするものなのだろうか。
小柄で太った躯を無理してかがめて、福山は野卑な笑いを殺しながらもうーつの闇の中に佇んでいた。
尚彦に来栖から主役にと声がかかった時、彼は夢を見ているのかと思った。
彼は街にあるありつたけの美しい花をこの幸福のために買い求めたい衝動にかられた。おそらく彼には一番相応しい喜びの表現であったろう。好んで花柄の模様の肌着を付ける彼には芳しい花束が一番似合った。
その知らせを聞いてしばらくして後、尚彦は京都の叔父の公成の所に報告しに出かけた。
奥嵯峨に広い家を持つ公成に会いに行くことは、彼にとっては東京の父の家に居る時よりも親密感を覚えるのだった。
公成は京都ではきこえた数奇者であった。兄の艸人とは違ってかっぷくの良い大らかな性格で、いかにも趣味三昧に明け暮れる暇人にあう体躯であった。
彼は少々の株で生活をし、いくつかの会社の役員を兼ねている以外、これといった仕事はしていなかった。
広い敷地の中で自分の好きかってな事をして日々を過ごしていた。尚彦は自分の兄弟の誰よりもこの叔父を高く評価していた。
叔父はいつものよぅに裏庭にある茶室に彼を招き入れた。
「そうか、尚彦、いよいよ主役か。わしも是非見させてもらおう。」
鷹揚な話し方だが、いかにも好事家が陶器をながめるように目を細めて尚彦を見た。
「乗栖瓏という有名な演出家に選ばれたんですからね。あの人に舞台を見てもらうだけでも大変なのに、その主役に選ばれたんだから、正直いって戸惑っています。」
「戸惑うとはお前らしくもないが、それだけ大変な舞台になりそうだな」
一服できあがって、ゆっくりと尚彦にすすめた所で、公成は改めて尚彦の顔を見た。
『知足庵』という名をつけられたこの茶室は自慢するだけあって、いたる所に贅がこらされていた。しかし、それを見抜くだけの力を尚彦は持っていなかった。
手仕鉢に流れる水のせせらぎが遠くで聞こえた。
広大な竹林の中に作られた茶室ゆえ、外からは草庵に見えるが中はまったく舌を巻く程の華麗な趣味がこらされている。
利休好みを公成は極端に嫌った。わび、さびの極地など捨ててしまえと言うのが公成の口癖であった。
けっして正式な作法を強いるわけでなく、すべて自由なま、無作意に茶を点ずるところが、若い尚彦には気が楽であった。
初夏の日ざしが切り通しから入って風炉を明暗に分けた。
風が庵の中をわたっていった。
「だが、お前なら出来るだろ。しっかりやることだな。」
茶碗の底に残った渋味を舌の先で味わっていた尚彦に公成は声をかけた。
「舞台の事は良く判らんが、その男の名前だけは聞いたことがあるな」
「演劇だけではありません。自分で能をやるとのことですよ。」
「能もやるのか……。」
来栖瓏という人物のことがようやく頭の中で反芻し始めた。しばらく空虚に風炉の水をながめるとでもなくしていた公成は、しかしそれが無駄なことであることを知った。
彼の記憶の中でそれらしき人物の面影は浮んで来なかった。
「東京の家には知らせたのか。」
「いいえ、まだです。その内に連絡でもしておきます。」
「まあ、お前が東京を嫌うのはわかるが、そろそろ兄も年老いて来た。少しは顔を見せてやることだ。」
「そうします。」
「お前が役者になるのを一番嫌ったのは東京の家だが、わしはお前の中に役者の血みたいなものがあると思っていたよ。たとえ、本家とは疎遠になってもな。役者にさせた方が良いと思っていた。これはやはり何かの縁だったかもしれないな。」
空ろな声が庭に響いた。
昨夜の雨の跡なのかまるい水滴が苔について、点々と光の結晶を作った。
尚彦は茶室の向こうに広がる奥庭が好きであった。こうしてここで坐っている時はそう広く見えないが、にじり口前の飛石から一歩足を庭に踏み入れると、だまし絵のように樹蔭から樹蔭へと路地が続いて、傾斜のなだらかな奥の庭に続く。
それを秘苑のように感じ取ったのは、まだ彼が苦かったからである。奥から見ると茅葺きの庵も壮大な家敷も見えなかった。
それを叔父に話した時、色めいて笑われた。
庭園の美というものが、その庭を愛でる人の心の投影に他ならない事を知らなかったのである。
もう一つ、尚彦にはその庭に想い出があった。
ある時、茶室の路地をぬけた奥庭で裸身の青年と出会った。
永い同、仏門にあずけられていた正円であった。
名刹として名高い大津の寺に幼ない頃よりあずけられていた。痩身で肌は透き通るように白かったが、修行で鍛えたのか力瘤ができていて、その温和な顔には似つかわしくなかった。わけあって、公成が他家の娘と交じあった未に出来た子であった。その後に娶った妻はすでに亡くなり、その女との間には子がなかったため、正式に入籍させようとしたものの正円の方が断ったらしい。
しかし、公成は自分のただ一人の実子である正円にひどく目をかけていた。
尚彦には年上の従兄にあたった。
正円は小さい頃から音楽に才能を表わし、独学で音楽論を修めた。天賦の才が彼をして作曲家としての立場を高らしめた。
尚彦は京都に居る時は、しばしば比叔の裾野にある正円の工房を訪ねた。
庭園で初めて正円と会った時の姿が忘れられなかった。
「座禅をくんでいたもので、とんだとこ
ろをお見せしました。」
正円は坊主頭を涼しげにかき上げながら急いで白い着物をつけた。
髭剃りあとの青さが眩しい。
きちんと折り目正しい礼儀というものを、年少のあどけなさを残した青年にまで、忘れずに、括淡として言葉をかける姿にひかれた。
清澄な響き。その声がまるで音色を奏でるように澄んでいた。
白い着物が庭の緑とあった。
若い尚彦はその時自分が何を話したのか、また何を正円は話してくれたのか、まったく覚えていなかった。
ただ強烈な印象は、白く透き通る肌と涼しげな瞳と人を酔わせる横笛に似た声であった。
古田正円の名を夏が近づくと必ず彼は想い起した。
尚彦にとつて夏は白い陽炎から始まるのであった。
神 話
京都の叔父の家を辞した翌日、尚彦は東京にもどつた。そして彼の植物園から珍らしい品種のライラックを選んだ。
彼は来栖瓏と初めて会った。
手にした花を見て来栖は助手に言いつけて、外に放り出させた。
花は乱れて散った。
来栖は青年の頬をうった。
一瞬、尚彦は忙然と立ちつくした。彼には目の前で飛び散った紫色の花房しか見えなかった。
あまりに残酷すぎる美しさにまわりの者も半ば放心して立ちつくした。
しかし、尚彦にはその仕打ちだけ十分であった。
来栖が彼に何を言いたいのかはっきりと知った。そして自分が今から花も植物さえない荒地に足を踏み入れなければらない運命にあることを悟った。
舞台の一角でもうーつの瞳が彼方か来栖の顔を見続けていた。
白い更紗をつけた古田正円の目である。彼はこの劇の音楽の全曲の作曲を依頼されていた。
来栖の指の動きにあわせて、正円は音楽の効果を微妙に変えていく。来栖の頭の中にある音を正円が楽譜にに作り直す。
二人の呼吸がピッタリとあわないとこれ程の微妙な感情の盛り上りは表現できない。
闇の中で見かわす目と目。熱く愛を語るような潤んだ瞳が闇の中でもつれ合う。余人からはまるでこの二人が濃厚なデュエットをしているかのように映っただろう。
しかし、実際にはこの情事に謹も気づきはしない。
舞台がいよいよエピローグに向って激しく熟を帯びで来たからである。
『ベガソスよ。』
目から血の涙を流したベレーロポンテースが言葉を繋いだ。
『もうそろそろここら辺で良いだろう。』
『何んでございましょうか。』
『もう歩く事には産れた。俺を早く処刑してくれ。』
『………』
『お前が父上から頼まれて、俺を殺しに来たことは判っている。』
『父上様からあなた様にお伝えすることがあります。』
『ほう、この俺を、こんな不遇な思いにさせた父親が、何をこの俺に言い伝えることがあるのか
見ろ、この俺の格好を!
お前にはよく見えるだろう。かつてミュケナイにこの俺と同じ位気品の高い勇者はいなかった。金色に輝く髪をアイロスの見になびかせて飛びまわっていた頃がなつかしい。
しかし、今はこのザマだ。襤褸(ぼろ)切れのよぅだ。』
『美はいつかは崩び去るものです。』
『なんだと。』
『もともとこの世に永遠の美などはあるのでしょうか。あなた様はそれをお求めになったのです。』
『そうか、ハハハ、そうか、ベガソスよ。お前はこの世に本当の美がないというのか、それではこの俺は何のために戦って来たんだ。』
ベレーロポンテースは真から可笑しそうに笑った。が、すぐに悲痛な顔にもどった。
『だが、そんなことは今ではどうでも良い。俺は両目を失った。今さら何も見えん。
さあ、それより親父のその伝言とやらを開かせてもらおうか。』
『ずっと昔、あなた嫌が生まれた頃に神託がありました。
それによると、この子は神に背く大罪をおかす。よって懲罰を受けるであろう。しかし、殺してはならぬ、また自ら命を絶ってもならぬ。
そう言う御神託があったのです。
それでオリュンポスの神々が父上に申しっけられた事は、この世の外に追放し、永久にその土地を彷徨うこと、けっして何も見えず聴こえず、そして話すことのない時間だけを与えよ、と言うことでした。』
『父上が俺にそう伝えろと言われたのか。』
『そうでございます。』
『そうか。』
『自分の運命を知らせないで、ただ生ることを強いることを不憫に思われたのでしょう。』
『そうか、父上によろしくと伝えてくれ。』
『私の使命は終りました。ここでお別れいたします。』
『行くが良い。老いたベガソスよ。あちょっと待ってくれ。風上はどっちの方なんだ。』
ベガソスは暗闇の一角を指した。
『あなた様が今向かわれている方です。』
『こうしていると風が頬をうって気持ちが良い。』
『もうじき嵐が来ます。』
『もう行ってくれ。俺はここで坐って俺の運命をじっと待っていよう。』
『お別れいたします。ご主人様。』
ベガソスは闇の中に消えた――。
来栖の両眼がカッと見開いた。
片手が虚空をよぎつた。
大音響とともに砂嵐が巻き上った。地鳴りをともなった嵐が雷雲を呼び、ゴーという唸りとともに砂塵を舞い上がらせ、凄まじい轟音が頭上を駆け巡った。耳を砕かんばかりの爆音が鼓膜をうった。
青いレーザー光線が四方八方に乱れ飛び、乱反射しながら、また細かく破片のように飛び散った。
闇と風と火花と轟音が、渦巻く怒濤のような抽象画を思わせた。
観客は自分がどこに坐っているのかを見失って青ざめた。
来栖の手が再び闇を切って正円を指した。
この大音響の中で一人瞑想しているかのような正円は、淡々として汗ひとつ浮かべすにマスターテープに手をかけた。
今、目の前で行っている修羅場を創り出している男とはとても思えなかった。
嵐の中心の静かな目の中にただ一人正円は居た。
白い指がスウィッチに触れる。
嵐の大きなうねりがゆっくりと引いて行き、それに替って波の砕ける音が舞台の底から響いた。
鴎(かもめ)の鳴く声が聞こえる。
青空に白い波しぶきが飛ぷ。
其青のフロリダの海岸が突然暗闇の中から現われた。
サーフボードを抱えた陽焼けした青年たちが街路を行き来している。
真夏の丁度、正午。
道は真白く輝き、目を開けるとその白さが目に痛い。
砂浜から若いい女の歓声が聞こえる。
蔭ひとつない大通りを盲目の吃喰が身に襤褸をまとい、どこに行くでもなく足を引きずりながらヨロヨロと歩いている。
車がクラクションをならすが聞こえないらしく、怒鳴り散らして避けて行く。
石に躓いて転んだその男の顔は生気のぬけた、もはや老年のそれに近いようであった。
起き上ろうとしても手と脚とが思うようにいかず、ただ躓くだけである。
夏の陽の光の中で、何もかも美しかったがこの男だけは醜悪であった。
丁度、ヤドカリがひっくり返ったように、空しく白い土を掻(か)いているだけだった。
彼は自分の姿に絶望したのか、そこに蹲ったまま動かなくなった。
高い陽がジリジグと屑のような男を灼いた。
一人の少年が男に声をかけた。
男が耳が開こえないのを知った少年は、持っていたハイビスカスの花で男の顔を●った。
埃まみれの目が一瞬動いた。
『おじさん、僕に掴まんなよ。』
少年は男を引っばって立たせると、肩に手をあてさせた。
『向こうにある白い教会に行くんだろ。』
少年は形の良い口唇で話しかけた。笑った顔から白い歯がこばれた。
『あっちが青い海だよ。おじさんどつちから来たんだ。』
男は少し立ち止って何かを見ようとして首をまわした。
海からの熱い風が頼をうった。
男は絶望したかのように立ち止った。
『さあ、おじさん行くよ。』
少年は笑いながら声をかけた。男は空しく頷くだけだった。
前 兆
『ほう、その劇は蝉丸だな。救いがない。』
いつものように磊落に話しながら、代赫(ぜん)の絣(かすり)を着た公成は応えた。
来栖の劇は大成功をおさめた。
彼の劇は新鮮だった。叙事的で因縁的であるにもかかわらず現代劇として十分に堪能できるのは、何よりも人間の業を絶えずテーマとしていたからである。
しかし、劇の成功は主役を演じた尚彦の力によるところもあった。多くの賛辞の慶びを彼は隠そうとはしなかった。
が、ふと我に遣ると、なぜあのような凄じい舞台が踏めたのか自分でも判らない。
おそらく来栖先生の指導がよかったのだろう。あの人の目を見つめでいると、他の物に目が行かなくなる。灼きつくような目、鋭く詰問する目である。
その緊張に耐えられないと思ったことが何度もあった。が、その度に来栖の醒めた目にぷつかった。
底知れぬ深さを湛えた目が、じつと彼を射貫いた。
尚彦はその度に痙えた。やがてその痙攣は甘美な陶酔に変った。
また一人、来栖は若く美しい蝶を手のひらに掴んだ。青い粉を思う存分、手のひらに飛び散らせて、その蝶は天鵞絨(ビロード)色に輝いた。
彼は尚彦を見つめていた。
それは演出家としてというよりも、もっと別の目で奥深い所を見つめているようであった。
「能の弱法師(よろぼうし)にはまだ父親との邂逅がある。」
能の素養がない尚彦にも、この有名な出し物がどんな内容であるかは知っていた。
夏の庭に公成の野太い声が響いた。
「げにも此の身は盲目の、足弱車の片輪ながら、よろめき歩けば弱法師と名づけたまうことわりや〜〜〜」
永年、暇にまかせて育っただけに公成の謡いには素人とは思えない艶と芯があった。
蝉丸は幼い頃から目が不自由であった。父の帝の今命によって不幸にも山に捨てられる。
長い放浪の未にようやく昔別れたきりになっていた姉と会う。しかし、それもつかの間で、またしても姉は去って行ってしまう。また一人孤独に山の中で生活をしなければならない運命が蝉丸には待っている、という筋である。
尚彦もその悲劇を叔父から聞かされることがあったが、自分が演じた今回は、少しの情緒さえない、もっと渇いた、冷たいものがあった。
おそらく、それは来栖の凄まじい業がそうさせたのだろう、と尚彦は思わざるをえなかった。
「お前は、劇の最後で盲目になって彷復い歩く時、彼に何か言われなかったか。」
「波の音を聴け、風の音を聴け、それを感じたら自分の瞼の中に陽の光りを見ろ、日輪を見よ、と言われょした。」
「成程、来栖は余程能が好きらしいな。」
「不思議ですよ。そうやって目をつぶると本当にフロリダの海岸彷徨っている気になるんですよ。」
「一度会ってみたいものだ、その男に。」
「機会があったら是非、叔父さんと会ってもらいたいですね。そうそう、僕も正円さんから紹介してもらった方がよいでしょう。なにせ、今回の芝居の成功もやっばり正円さんの音楽が大変な効果を産んだからですよ。」
事実、尚彦は本当にそうだと思った。
これは舞台の上で演じた者にしかない感覚であろう。
尚彦の気持ちが高よれば高まるように正円は官能の音を高める。尚彦の動きがすべて正円の音に包みこまれている。
正円は自分の音で尚彦の躯をじっくりと堪能していもかのよぅであった。
女の手よりも柔かな音色で素肌を愛撫される気がした。音楽の性的な陶酔というのがあるとしたら、正円が創りだす悠久の音色がそれではないだろうかと尚彦は確信していた。
が、尚彦にはまだ判然としないものがあった。
来栖と正円のことである。
他の助手たちには必要以上に激しい彼であったが、正円に対してはまったく何の注文もつけない。
稽古の時にも来栖は正円を無視するかのように音楽に関しては何も言わなかった。
もともと無口な正円も来栖にはまったく話しかけることはなかった。
人々はこの二人の才人が反撥しあっていると噂した。しかし、尚彦には二つの大きな妖星が、互いに引力を出して劇の均衡を保たせているように思えた。
嵐と大海原のような微妙な駆け引きが二人の問に炎をつくつている。
おばろに、二つの面が浮かんだ。
 一つは泥眼(でいがん)、また一つは深井(ふかい)の面である。
一つは泥眼(でいがん)、また一つは深井(ふかい)の面である。
尚彦は能の演目を想い出した。
泥眼という仮面は、眼の縁に金泥を塗って妖しさを表わす面である。恋に燃える、嵐のような激しさを表現する。
能では『葵の上』の面として使われる。
それに対して深井の方は『野宮』の出し物の中でつける静かな面である。
来栖と正円に、この二つの面が重なって映った。
けっして自分の感情を表面に出さない、兼朴で幽玄なる趣きを秘めた野宮の面。
それは小さい頃から正円の凛々しい姿に抱いでいた面影と重なりあった。
が、葉上を悩ます霊の姿として出る泥眼の方はどろどろとした情念が映された、憎悪の念がこめられている面である。
しかし、この面には人を誘う強い魅力がある。尚彦には、それは来栖を思い起こさせた。
美しい者に睨まれながら、力を失ってしまう魅力である。
どちらも美しい、と尚彦は想った。
荒々しく人を掴んで離さない炎の力、静かな夕凧ぎのような、広大な引潮を感じさせる沈黙の量感。
躊踞(つくばい)の向こぅの木立で蝉が鳴いた。
盛夏にはまだ時間があるのに、この夏はずいぶんと早い。
それは尚彦の心の充実感でもあった。
正円さんの所にでも久しぶりに訪ねてみようか。
尚彦は比叡の方に目をやった。
彼の目には青い山なみだけが映った。
澄んだ目には、まだ人の修羅を知らない清々しさがあった。
伸び伸びと育つ青年を眩しい目で公成は見ていた。
しかし、数奇者の裡には、珍らしく心にひっかかるものがあった。
深井も泥眼も、実は一人の人物人ぞれの顔であることを尚彦は知らないでいるのだろう。
この能の後半が、おどろおどろしい恋の復讐心にとり憑れた般若のくだりになることを。
公成は、若い尚彦には別に教える必要もないと思った。
躊踞に火がついた。
西陽が、丁度躊踞の水に反射し紅に染めた。水が溢れて遺木に流れこんだ。
炎が庭に広がる。
これ以上、燃えなければ良いが……。
公成は、炎を見ながらそう思った。
←戻る 進む→
漆黒の闇だった。
あたり一面を覆う暗闇が、一瞬にして観客を沈黙させた。鼻をつく闇とはおそらくこの事をさすのだろう。空も大地もなくあらゆる人の目の届く限り壁のような闇であった。
ほんの少し前、舞台は燦然と輝く陽の光を浴びて緋色に染った。
天を翔ける金色の髪毛を長く書かせた
勇者ぺレーロポンテースが、愛馬とともに天まで登ろうとした。
その一瞬、主神ゼウスの怒りに触れたぺレーロポンテースは失墜して燃えた。
突然、轟音がとどろき、舞台は赤く燃えた。目を潰す眩しさに観客は思わず手をかざした。
青年の燃えて行く様は、まるで炎の鳥のように美しく、火の尾羽を長くひきながら弧を描いて地に堕ちた。
青い瞳が燃え上り、珊瑚のように美しい口唇に火がつき、髪毛が輝いた。小さな叫びを残して青年は奔馬とともに奈落に消えていった。
人々は闇の海に取り残された。
しばしの深い静寂の中で、先程の美の主人公の余韻を楽しんだ。そして、ようやくこの大作「ぺレーロポンテース」が終曲になったことを悟った。
音楽だけが、闇の中で響く。
深い藍、さめるような青い色を思わせる音。水の中を漂うように、躯がふわりと浮び上がる。
が、闇の中で二つの目だけが冷たく光っていた。
おそらく、この舞台のどのライトよりも強く役者の動きをひとつひとつくさすように見つめる目。醒めている瞳の奥で、炎が燃え上っていた。
恐しい程の眼差。張りのある瞳。
この眼差しで見つめられたら、どんな獰猛な獣でさえ怖気づいてしまうことだろう、と演出の助手たちはいつも思うのである。しかし、来栖瓏という演出家に付いていられるだけでも彼らは満足していた。
彼らは、この若くして国際的な名声を博している演出家の秘技に少しでもあやかろうと、先を争って助手を志願した。と同時に、あまりのスケールの大きさに肝をぬかして、立ち去っていく者が後を絶たなかった。
確かに、このエネルギイッシュな演出家にあわせようとしたならば、おそらく並の神経では勤まらないだろう。
彼は常に動いていた。
動くことによって自分のイメージを創り出す。指先で指示する時には頭の中にはもう何頁か先のシークエンスが広がっている。
完全主義者であり、すべてに完成された美こそが絶対だと信ずる宗教的なファナチィストでもあった。
彼の白い爪先が瞬時に空を切った。
闇の中におばろげに二人の人物が杖をたよりに現われた。
先程の勇者の面影はまるでなく、ヨロヨロと力なく歩いてくる。煤けた顔をして、痩せこけた胸をあらわにしたペレーポンテースがスポットライトに照らし出された。
燦然と輝いて金色の髪も汚れて汗ばんでいる。彼らが歩くたびに赤茶けた砂が舞い上る。
従者であろうか年をとった男が肩をかしながら、美貌の青年を辛うじて支えていた。
「ペガソスよ。ペガソスよ。どこに居る。」
青年の弱々しいが凛とした声が響いた。
『ご主人様、ああ、おいたわしい。』
『ペガソスか、私は目をやられたらしい。何も見えない。』
『ああ、おいたわしや、ご主人様。私はここに居ります。』
『ここに、ここに居るというのは……この艶のない顔、縮れた老人の髪の毛をしたお主がそうだと言うのか。』
『そうでございます。』
『ハハハ、何を馬鹿なことを言っているのだ。』
青年の両眼から血の涙が流れた。
『どこの誰だか知らぬが救えてやろう。いいか、ペガソスというのは、すばらい戦士で、俺と一緒に連戦に連戦を重ねた。四肢の肉の良く張った屈強な奴だ。誰がお前のような老いぼれと一緒なものか
コリントスで戦った時も、そうだ、あのリユキアでの戦さの時も、俺と一緒に奮戦したものだ。疲れを知らなかった奴だ。』
『そうでございます。あなた様はあの青鷺の羽を一本右の胸にさされで出陣なさいました。それにキマイラとの戦いの最中、私を助けていただいたことがごいます。』
『コリントスで戦った時も、そうだ、あのリユキアでの戦さの時も、俺と一緒に奮戦したものだ。疲れを知らなかった奴だ。』
『そうでございます。あなた様はあの時、青鷺の羽を一本右の胸にさされて出陣なさいました。それにキマイラとの戦いの最中、私を助けていただいたことがございます。』
『キマイラとの……。』
『そうです、ご主人様。あなたのそばにずっとお仕えしておりょしたのは私でございます。
そうやって両の目が潰れて初めて、あなた様は私の本当の姿を見ることができたのです。』
『そうか、永い間俺のそばに居たのはお前であったか……。ハハハ。』
青年は痴呆のようにだらしなく笑った。
『皮肉なものだな。こうやってどことも判らない場所を彷徨いながら、俺は初めて自分を判ったような気がするぞ。』
青年はベガリスの肩から離れると、杖を片手によろけながら舞台の其ん中に進んだ。そして頭を少しばかり上けた。
またしても乾いた砂が舞い上がった。
『風が吹いているのか。お前には何か見えるか。』
『いいえ、私にも何も見えません。闇です。あなた様が見つめていられる闇よりも、まだ深い闇です。』
『そうか。もうずっと昔だ。そぅだな子供の頃に父に開かされたことがあった。こうやって頭を上につきあげて、もし風が吹いていないとしたら、そこがお前の死ぬ場所だとな。』
観客席には咳ひとつおこらなかった。
それ程までに、この劇のエピローグには予感があった。
じっと主人公の演技に目を注いでいた来栖の瞼は閉ざされていた。何かを待ちのぞんでいるかのように、じつと音楽を聴いていた。
助手たちは、閉ざされた瞳の臭で何を考えているのかを訝しんだ。劇よりももっと残忍でもつと忌しい虚無が彼を捉えていることだけは確かであった。
白い陽炎
舞台の下手でプロデューサーの福山が一人悦にいっていた。
最初、この劇に来栖が駆け出しの役者を使うといった時には、さすがに反対した。何よりも今回の劇には主役の持ち場面が多く、それだけに熟練さが要求されてくる。そんな所に何回か噂されたことがあるかも知れないにしろ、まだまだ未熟な俳優を使うことは危険が大き遺ぎた。
しかし、来栖は若い役者を強く薦した。
名を室生尚彦と言う。ようやく売りだし始めた役者であった。
福山は渋々承諾した。いくら彼が横ヤリを入れたとしても耳をかすような相手ではなかったからである。それに尚彦が高名な戯曲家の艸人の息子ということも、少なからず彼の計算の中にはあった。
『まあ、やらせてみるとするか。』
彼の裡にはすでに次のプランがあった。前からこの老大家の戯曲をどうしても手掛けたかった。もうすぐでき上る国立オペラ劇場の柿(こけら)落しでその戯曲を上演したかったのである。
だから、少々危険な賭であるが尚彦を主役に抜述するにはやぶさかではなかった。
『それにしても……。』
福山は一人でほくそ笑んだ。これ程までに尚彦が力強い演技を見せるとは思わなかった。
「ハガネのような躯だ」と、栗栖がもらしたことがあったが、やはり血筋が良いのだろうか、正直なところ福山も舌を巻いた。けっして躊躇するところがない。若さというのはこうも人を神がかりにするものなのだろうか。
小柄で太った躯を無理してかがめて、福山は野卑な笑いを殺しながらもうーつの闇の中に佇んでいた。
尚彦に来栖から主役にと声がかかった時、彼は夢を見ているのかと思った。
彼は街にあるありつたけの美しい花をこの幸福のために買い求めたい衝動にかられた。おそらく彼には一番相応しい喜びの表現であったろう。好んで花柄の模様の肌着を付ける彼には芳しい花束が一番似合った。
その知らせを聞いてしばらくして後、尚彦は京都の叔父の公成の所に報告しに出かけた。
奥嵯峨に広い家を持つ公成に会いに行くことは、彼にとっては東京の父の家に居る時よりも親密感を覚えるのだった。
公成は京都ではきこえた数奇者であった。兄の艸人とは違ってかっぷくの良い大らかな性格で、いかにも趣味三昧に明け暮れる暇人にあう体躯であった。
彼は少々の株で生活をし、いくつかの会社の役員を兼ねている以外、これといった仕事はしていなかった。
広い敷地の中で自分の好きかってな事をして日々を過ごしていた。尚彦は自分の兄弟の誰よりもこの叔父を高く評価していた。
叔父はいつものよぅに裏庭にある茶室に彼を招き入れた。
「そうか、尚彦、いよいよ主役か。わしも是非見させてもらおう。」
鷹揚な話し方だが、いかにも好事家が陶器をながめるように目を細めて尚彦を見た。
「乗栖瓏という有名な演出家に選ばれたんですからね。あの人に舞台を見てもらうだけでも大変なのに、その主役に選ばれたんだから、正直いって戸惑っています。」
「戸惑うとはお前らしくもないが、それだけ大変な舞台になりそうだな」
一服できあがって、ゆっくりと尚彦にすすめた所で、公成は改めて尚彦の顔を見た。
『知足庵』という名をつけられたこの茶室は自慢するだけあって、いたる所に贅がこらされていた。しかし、それを見抜くだけの力を尚彦は持っていなかった。
手仕鉢に流れる水のせせらぎが遠くで聞こえた。
広大な竹林の中に作られた茶室ゆえ、外からは草庵に見えるが中はまったく舌を巻く程の華麗な趣味がこらされている。
利休好みを公成は極端に嫌った。わび、さびの極地など捨ててしまえと言うのが公成の口癖であった。
けっして正式な作法を強いるわけでなく、すべて自由なま、無作意に茶を点ずるところが、若い尚彦には気が楽であった。
初夏の日ざしが切り通しから入って風炉を明暗に分けた。
風が庵の中をわたっていった。
「だが、お前なら出来るだろ。しっかりやることだな。」
茶碗の底に残った渋味を舌の先で味わっていた尚彦に公成は声をかけた。
「舞台の事は良く判らんが、その男の名前だけは聞いたことがあるな」
「演劇だけではありません。自分で能をやるとのことですよ。」
「能もやるのか……。」
来栖瓏という人物のことがようやく頭の中で反芻し始めた。しばらく空虚に風炉の水をながめるとでもなくしていた公成は、しかしそれが無駄なことであることを知った。
彼の記憶の中でそれらしき人物の面影は浮んで来なかった。
「東京の家には知らせたのか。」
「いいえ、まだです。その内に連絡でもしておきます。」
「まあ、お前が東京を嫌うのはわかるが、そろそろ兄も年老いて来た。少しは顔を見せてやることだ。」
「そうします。」
「お前が役者になるのを一番嫌ったのは東京の家だが、わしはお前の中に役者の血みたいなものがあると思っていたよ。たとえ、本家とは疎遠になってもな。役者にさせた方が良いと思っていた。これはやはり何かの縁だったかもしれないな。」
空ろな声が庭に響いた。
昨夜の雨の跡なのかまるい水滴が苔について、点々と光の結晶を作った。
尚彦は茶室の向こうに広がる奥庭が好きであった。こうしてここで坐っている時はそう広く見えないが、にじり口前の飛石から一歩足を庭に踏み入れると、だまし絵のように樹蔭から樹蔭へと路地が続いて、傾斜のなだらかな奥の庭に続く。
それを秘苑のように感じ取ったのは、まだ彼が苦かったからである。奥から見ると茅葺きの庵も壮大な家敷も見えなかった。
それを叔父に話した時、色めいて笑われた。
庭園の美というものが、その庭を愛でる人の心の投影に他ならない事を知らなかったのである。
もう一つ、尚彦にはその庭に想い出があった。
ある時、茶室の路地をぬけた奥庭で裸身の青年と出会った。
永い同、仏門にあずけられていた正円であった。
名刹として名高い大津の寺に幼ない頃よりあずけられていた。痩身で肌は透き通るように白かったが、修行で鍛えたのか力瘤ができていて、その温和な顔には似つかわしくなかった。わけあって、公成が他家の娘と交じあった未に出来た子であった。その後に娶った妻はすでに亡くなり、その女との間には子がなかったため、正式に入籍させようとしたものの正円の方が断ったらしい。
しかし、公成は自分のただ一人の実子である正円にひどく目をかけていた。
尚彦には年上の従兄にあたった。
正円は小さい頃から音楽に才能を表わし、独学で音楽論を修めた。天賦の才が彼をして作曲家としての立場を高らしめた。
尚彦は京都に居る時は、しばしば比叔の裾野にある正円の工房を訪ねた。
庭園で初めて正円と会った時の姿が忘れられなかった。
「座禅をくんでいたもので、とんだとこ
ろをお見せしました。」
正円は坊主頭を涼しげにかき上げながら急いで白い着物をつけた。
髭剃りあとの青さが眩しい。
きちんと折り目正しい礼儀というものを、年少のあどけなさを残した青年にまで、忘れずに、括淡として言葉をかける姿にひかれた。
清澄な響き。その声がまるで音色を奏でるように澄んでいた。
白い着物が庭の緑とあった。
若い尚彦はその時自分が何を話したのか、また何を正円は話してくれたのか、まったく覚えていなかった。
ただ強烈な印象は、白く透き通る肌と涼しげな瞳と人を酔わせる横笛に似た声であった。
古田正円の名を夏が近づくと必ず彼は想い起した。
尚彦にとつて夏は白い陽炎から始まるのであった。
神 話
京都の叔父の家を辞した翌日、尚彦は東京にもどつた。そして彼の植物園から珍らしい品種のライラックを選んだ。
彼は来栖瓏と初めて会った。
手にした花を見て来栖は助手に言いつけて、外に放り出させた。
花は乱れて散った。
来栖は青年の頬をうった。
一瞬、尚彦は忙然と立ちつくした。彼には目の前で飛び散った紫色の花房しか見えなかった。
あまりに残酷すぎる美しさにまわりの者も半ば放心して立ちつくした。
しかし、尚彦にはその仕打ちだけ十分であった。
来栖が彼に何を言いたいのかはっきりと知った。そして自分が今から花も植物さえない荒地に足を踏み入れなければらない運命にあることを悟った。
舞台の一角でもうーつの瞳が彼方か来栖の顔を見続けていた。
白い更紗をつけた古田正円の目である。彼はこの劇の音楽の全曲の作曲を依頼されていた。
来栖の指の動きにあわせて、正円は音楽の効果を微妙に変えていく。来栖の頭の中にある音を正円が楽譜にに作り直す。
二人の呼吸がピッタリとあわないとこれ程の微妙な感情の盛り上りは表現できない。
闇の中で見かわす目と目。熱く愛を語るような潤んだ瞳が闇の中でもつれ合う。余人からはまるでこの二人が濃厚なデュエットをしているかのように映っただろう。
しかし、実際にはこの情事に謹も気づきはしない。
舞台がいよいよエピローグに向って激しく熟を帯びで来たからである。
『ベガソスよ。』
目から血の涙を流したベレーロポンテースが言葉を繋いだ。
『もうそろそろここら辺で良いだろう。』
『何んでございましょうか。』
『もう歩く事には産れた。俺を早く処刑してくれ。』
『………』
『お前が父上から頼まれて、俺を殺しに来たことは判っている。』
『父上様からあなた様にお伝えすることがあります。』
『ほう、この俺を、こんな不遇な思いにさせた父親が、何をこの俺に言い伝えることがあるのか
見ろ、この俺の格好を!
お前にはよく見えるだろう。かつてミュケナイにこの俺と同じ位気品の高い勇者はいなかった。金色に輝く髪をアイロスの見になびかせて飛びまわっていた頃がなつかしい。
しかし、今はこのザマだ。襤褸(ぼろ)切れのよぅだ。』
『美はいつかは崩び去るものです。』
『なんだと。』
『もともとこの世に永遠の美などはあるのでしょうか。あなた様はそれをお求めになったのです。』
『そうか、ハハハ、そうか、ベガソスよ。お前はこの世に本当の美がないというのか、それではこの俺は何のために戦って来たんだ。』
ベレーロポンテースは真から可笑しそうに笑った。が、すぐに悲痛な顔にもどった。
『だが、そんなことは今ではどうでも良い。俺は両目を失った。今さら何も見えん。
さあ、それより親父のその伝言とやらを開かせてもらおうか。』
『ずっと昔、あなた嫌が生まれた頃に神託がありました。
それによると、この子は神に背く大罪をおかす。よって懲罰を受けるであろう。しかし、殺してはならぬ、また自ら命を絶ってもならぬ。
そう言う御神託があったのです。
それでオリュンポスの神々が父上に申しっけられた事は、この世の外に追放し、永久にその土地を彷徨うこと、けっして何も見えず聴こえず、そして話すことのない時間だけを与えよ、と言うことでした。』
『父上が俺にそう伝えろと言われたのか。』
『そうでございます。』
『そうか。』
『自分の運命を知らせないで、ただ生ることを強いることを不憫に思われたのでしょう。』
『そうか、父上によろしくと伝えてくれ。』
『私の使命は終りました。ここでお別れいたします。』
『行くが良い。老いたベガソスよ。あちょっと待ってくれ。風上はどっちの方なんだ。』
ベガソスは暗闇の一角を指した。
『あなた様が今向かわれている方です。』
『こうしていると風が頬をうって気持ちが良い。』
『もうじき嵐が来ます。』
『もう行ってくれ。俺はここで坐って俺の運命をじっと待っていよう。』
『お別れいたします。ご主人様。』
ベガソスは闇の中に消えた――。
来栖の両眼がカッと見開いた。
片手が虚空をよぎつた。
大音響とともに砂嵐が巻き上った。地鳴りをともなった嵐が雷雲を呼び、ゴーという唸りとともに砂塵を舞い上がらせ、凄まじい轟音が頭上を駆け巡った。耳を砕かんばかりの爆音が鼓膜をうった。
青いレーザー光線が四方八方に乱れ飛び、乱反射しながら、また細かく破片のように飛び散った。
闇と風と火花と轟音が、渦巻く怒濤のような抽象画を思わせた。
観客は自分がどこに坐っているのかを見失って青ざめた。
来栖の手が再び闇を切って正円を指した。
この大音響の中で一人瞑想しているかのような正円は、淡々として汗ひとつ浮かべすにマスターテープに手をかけた。
今、目の前で行っている修羅場を創り出している男とはとても思えなかった。
嵐の中心の静かな目の中にただ一人正円は居た。
白い指がスウィッチに触れる。
嵐の大きなうねりがゆっくりと引いて行き、それに替って波の砕ける音が舞台の底から響いた。
鴎(かもめ)の鳴く声が聞こえる。
青空に白い波しぶきが飛ぷ。
其青のフロリダの海岸が突然暗闇の中から現われた。
サーフボードを抱えた陽焼けした青年たちが街路を行き来している。
真夏の丁度、正午。
道は真白く輝き、目を開けるとその白さが目に痛い。
砂浜から若いい女の歓声が聞こえる。
蔭ひとつない大通りを盲目の吃喰が身に襤褸をまとい、どこに行くでもなく足を引きずりながらヨロヨロと歩いている。
車がクラクションをならすが聞こえないらしく、怒鳴り散らして避けて行く。
石に躓いて転んだその男の顔は生気のぬけた、もはや老年のそれに近いようであった。
起き上ろうとしても手と脚とが思うようにいかず、ただ躓くだけである。
夏の陽の光の中で、何もかも美しかったがこの男だけは醜悪であった。
丁度、ヤドカリがひっくり返ったように、空しく白い土を掻(か)いているだけだった。
彼は自分の姿に絶望したのか、そこに蹲ったまま動かなくなった。
高い陽がジリジグと屑のような男を灼いた。
一人の少年が男に声をかけた。
男が耳が開こえないのを知った少年は、持っていたハイビスカスの花で男の顔を●った。
埃まみれの目が一瞬動いた。
『おじさん、僕に掴まんなよ。』
少年は男を引っばって立たせると、肩に手をあてさせた。
『向こうにある白い教会に行くんだろ。』
少年は形の良い口唇で話しかけた。笑った顔から白い歯がこばれた。
『あっちが青い海だよ。おじさんどつちから来たんだ。』
男は少し立ち止って何かを見ようとして首をまわした。
海からの熱い風が頼をうった。
男は絶望したかのように立ち止った。
『さあ、おじさん行くよ。』
少年は笑いながら声をかけた。男は空しく頷くだけだった。
前 兆
『ほう、その劇は蝉丸だな。救いがない。』
いつものように磊落に話しながら、代赫(ぜん)の絣(かすり)を着た公成は応えた。
来栖の劇は大成功をおさめた。
彼の劇は新鮮だった。叙事的で因縁的であるにもかかわらず現代劇として十分に堪能できるのは、何よりも人間の業を絶えずテーマとしていたからである。
しかし、劇の成功は主役を演じた尚彦の力によるところもあった。多くの賛辞の慶びを彼は隠そうとはしなかった。
が、ふと我に遣ると、なぜあのような凄じい舞台が踏めたのか自分でも判らない。
おそらく来栖先生の指導がよかったのだろう。あの人の目を見つめでいると、他の物に目が行かなくなる。灼きつくような目、鋭く詰問する目である。
その緊張に耐えられないと思ったことが何度もあった。が、その度に来栖の醒めた目にぷつかった。
底知れぬ深さを湛えた目が、じつと彼を射貫いた。
尚彦はその度に痙えた。やがてその痙攣は甘美な陶酔に変った。
また一人、来栖は若く美しい蝶を手のひらに掴んだ。青い粉を思う存分、手のひらに飛び散らせて、その蝶は天鵞絨(ビロード)色に輝いた。
彼は尚彦を見つめていた。
それは演出家としてというよりも、もっと別の目で奥深い所を見つめているようであった。
「能の弱法師(よろぼうし)にはまだ父親との邂逅がある。」
能の素養がない尚彦にも、この有名な出し物がどんな内容であるかは知っていた。
夏の庭に公成の野太い声が響いた。
「げにも此の身は盲目の、足弱車の片輪ながら、よろめき歩けば弱法師と名づけたまうことわりや〜〜〜」
永年、暇にまかせて育っただけに公成の謡いには素人とは思えない艶と芯があった。
蝉丸は幼い頃から目が不自由であった。父の帝の今命によって不幸にも山に捨てられる。
長い放浪の未にようやく昔別れたきりになっていた姉と会う。しかし、それもつかの間で、またしても姉は去って行ってしまう。また一人孤独に山の中で生活をしなければならない運命が蝉丸には待っている、という筋である。
尚彦もその悲劇を叔父から聞かされることがあったが、自分が演じた今回は、少しの情緒さえない、もっと渇いた、冷たいものがあった。
おそらく、それは来栖の凄まじい業がそうさせたのだろう、と尚彦は思わざるをえなかった。
「お前は、劇の最後で盲目になって彷復い歩く時、彼に何か言われなかったか。」
「波の音を聴け、風の音を聴け、それを感じたら自分の瞼の中に陽の光りを見ろ、日輪を見よ、と言われょした。」
「成程、来栖は余程能が好きらしいな。」
「不思議ですよ。そうやって目をつぶると本当にフロリダの海岸彷徨っている気になるんですよ。」
「一度会ってみたいものだ、その男に。」
「機会があったら是非、叔父さんと会ってもらいたいですね。そうそう、僕も正円さんから紹介してもらった方がよいでしょう。なにせ、今回の芝居の成功もやっばり正円さんの音楽が大変な効果を産んだからですよ。」
事実、尚彦は本当にそうだと思った。
これは舞台の上で演じた者にしかない感覚であろう。
尚彦の気持ちが高よれば高まるように正円は官能の音を高める。尚彦の動きがすべて正円の音に包みこまれている。
正円は自分の音で尚彦の躯をじっくりと堪能していもかのよぅであった。
女の手よりも柔かな音色で素肌を愛撫される気がした。音楽の性的な陶酔というのがあるとしたら、正円が創りだす悠久の音色がそれではないだろうかと尚彦は確信していた。
が、尚彦にはまだ判然としないものがあった。
来栖と正円のことである。
他の助手たちには必要以上に激しい彼であったが、正円に対してはまったく何の注文もつけない。
稽古の時にも来栖は正円を無視するかのように音楽に関しては何も言わなかった。
もともと無口な正円も来栖にはまったく話しかけることはなかった。
人々はこの二人の才人が反撥しあっていると噂した。しかし、尚彦には二つの大きな妖星が、互いに引力を出して劇の均衡を保たせているように思えた。
嵐と大海原のような微妙な駆け引きが二人の問に炎をつくつている。
おばろに、二つの面が浮かんだ。
 一つは泥眼(でいがん)、また一つは深井(ふかい)の面である。
一つは泥眼(でいがん)、また一つは深井(ふかい)の面である。尚彦は能の演目を想い出した。
泥眼という仮面は、眼の縁に金泥を塗って妖しさを表わす面である。恋に燃える、嵐のような激しさを表現する。
能では『葵の上』の面として使われる。
それに対して深井の方は『野宮』の出し物の中でつける静かな面である。
来栖と正円に、この二つの面が重なって映った。
けっして自分の感情を表面に出さない、兼朴で幽玄なる趣きを秘めた野宮の面。
それは小さい頃から正円の凛々しい姿に抱いでいた面影と重なりあった。
が、葉上を悩ます霊の姿として出る泥眼の方はどろどろとした情念が映された、憎悪の念がこめられている面である。
しかし、この面には人を誘う強い魅力がある。尚彦には、それは来栖を思い起こさせた。
美しい者に睨まれながら、力を失ってしまう魅力である。
どちらも美しい、と尚彦は想った。
荒々しく人を掴んで離さない炎の力、静かな夕凧ぎのような、広大な引潮を感じさせる沈黙の量感。
躊踞(つくばい)の向こぅの木立で蝉が鳴いた。
盛夏にはまだ時間があるのに、この夏はずいぶんと早い。
それは尚彦の心の充実感でもあった。
正円さんの所にでも久しぶりに訪ねてみようか。
尚彦は比叡の方に目をやった。
彼の目には青い山なみだけが映った。
澄んだ目には、まだ人の修羅を知らない清々しさがあった。
伸び伸びと育つ青年を眩しい目で公成は見ていた。
しかし、数奇者の裡には、珍らしく心にひっかかるものがあった。
深井も泥眼も、実は一人の人物人ぞれの顔であることを尚彦は知らないでいるのだろう。
この能の後半が、おどろおどろしい恋の復讐心にとり憑れた般若のくだりになることを。
公成は、若い尚彦には別に教える必要もないと思った。
躊踞に火がついた。
西陽が、丁度躊踞の水に反射し紅に染めた。水が溢れて遺木に流れこんだ。
炎が庭に広がる。
これ以上、燃えなければ良いが……。
公成は、炎を見ながらそう思った。
←戻る 進む→